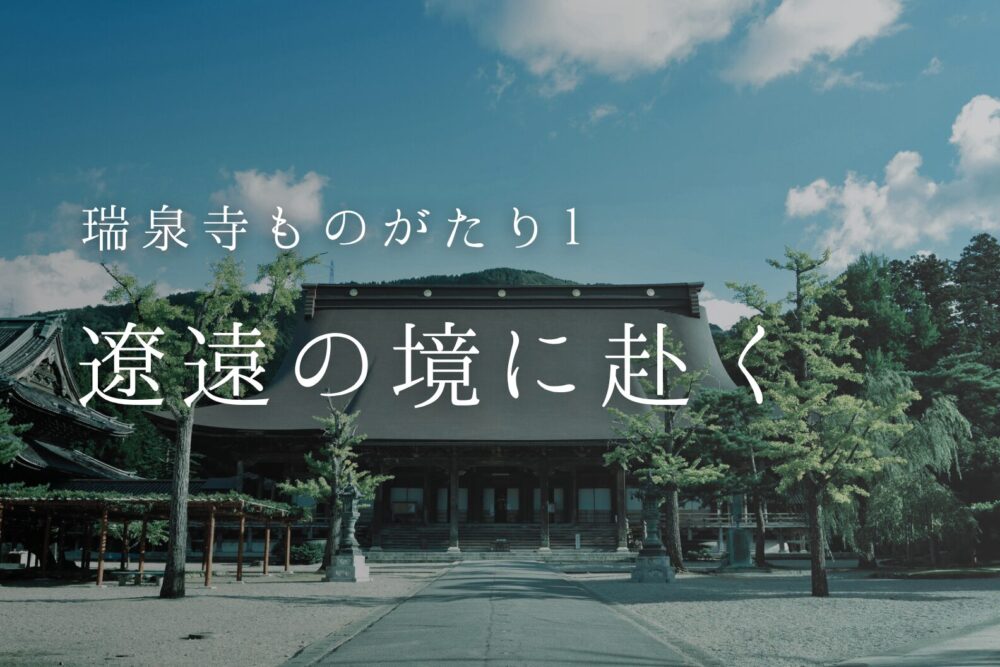
遼遠の境に赴く- 瑞泉寺ものがたり1
※本シリーズでは、全4回を通じて、瑞泉寺創建から現代に至るまでの歴史の流れを物語として描いていく。
時は室町、三代将軍義満の世
室町時代が始まって間もない14世紀末、京の都では足利義満が絶頂期を迎えていた。南北朝の争いに終止符を打ち、明国との貿易で富を蓄え、金閣を建てて北山文化を花開かせた義満。その治世の安定は、仏教界にも新たな展開をもたらしていた。
この頃、浄土真宗本願寺では綽如という一人の僧が頭角を現していた。
伝承によれば、綽如は1350年の生まれで、義満の正室となる日野業子の実家である名門・日野家に預けられた。業子とは幼い頃から親しく、また義満の片腕として活躍した斯波義将とも同い年だったという。真偽のほどは定かではないが、少なくとも綽如が時の権力者たちと密接な関係にあったことは間違いないようだ。
越中への道
越中国は当時、美濃から続く北陸道の要衝であった。足利義満はこの地の安定を重視し、室町幕府の有力守護大名である斯波氏を越中守護に任じた。斯波義将は、1379年から1397年まで管領を務めた実力者であり、越中・越前・若狭・能登の四カ国を支配する大大名でもあった。
伝承では、越中には南朝の残党勢力が根強く残っており、後醍醐天皇の皇子である恒良親王や、美濃から逃れてきた斎藤氏らが桃井氏を頼って砺波地方に潜伏していたとされる。義満はこれらの勢力を懐柔するため、武力だけでなく宗教的な影響力も必要と考え、綽如に白羽の矢を立てたとする説もある。
井波という土地
綽如が向かった井波は、決して布教に適した場所ではなかった。この地域は古くから天台宗と真言宗の勢力圏で、当時この地にあった止観寺やその末寺、さらには高瀬神社近くの専勝寺など、既存の宗教勢力が強固な基盤を築いていた。新興の浄土真宗が割って入る余地は、ほとんど見当たらなかった。
それでも綽如が井波に足を向けることができたのは、やはり斯波義将の後ろ盾があったからだろう。武力による平定だけでは民心の安定は得られない。宗教的な調停者として、綽如の存在は欠かせなかったのである。
綽如は「遼遠の境に赴く」という言葉を残したと伝えられている。遙か遠い辺境の地への覚悟を込めた、印象深い表現だ。彼はまず杉谷に小さな庵を結び、地元の人々との和睦交渉に当たったという。
勧進状という希望
転機が訪れたのは1386年のことだった。義満から重要な使命を託された綽如は、一時京都に戻ることになる。伝承によれば、明国からの国書の解読を依頼され、博識な綽如はこれを難なく解読し、機転の利いた返答までしたという。
この時、綽如が手にしたものは大きなものだった。それは「勧進状」と呼ばれる文書である。これは義満の支配下にある六ヶ国(越前、越中、飛騨、信濃、加賀、能登)の豪族たちから、寺院建立のための資金を集めることを許可するものだった。当時は後小松天皇の治世。義満が南北朝統一のために擁立し、巧みに操っていた天皇である。
この勧進状こそが、瑞泉寺創建への道筋を開いたのだった。
井波での9年間
興味深いことに、綽如は1384年に井波に下向してから、1393年に逝去するまでの9年間、目立った布教活動を行わなかったと伝えられている。これは一見不可解に思えるが、当時の既存の宗教勢力との摩擦を避け、地域に溶け込むことを最優先にしたのだろう。
急激な変化は反発を招く。綽如は長い時間をかけて信頼関係を築き、真の意味での宗教的基盤を固めていったのかもしれない。この忍耐強い姿勢こそが、後の瑞泉寺の繁栄につながったと考えるのは、いささか強引だろうか。
物語の始まりと謎
そうして1390年、越中国井波の地に瑞泉寺が創建された。これは確実な史実である。創建者が綽如であることも、複数の史料が一致して伝えている。
だが、綽如上人の生涯には悲劇的な最期が待っていた。創建から3年後の1393年4月24日、綽如は44歳の若さで逝去した。病弱であったため病没が定説とされているが、まことしやかに伝えられている説がある。南朝勢力残党の平定という政治的使命を帯びていたために、その南朝支持者によって井栗谷で惨殺されたというのだ。
さらに奇妙なことに、綽如の死後、瑞泉寺は45年間という長期にわたって無住職の状態が続いた。なぜこれほど長い間、後継者が置かれなかったのか。病死か暗殺か、そして長期無住職の理由。これらの謎は瑞泉寺の歴史に深い陰影を落としている。
史実と伝承の交錯
瑞泉寺の創建に至る物語は、史実と伝承が巧みに織り交ざった興味深いものだ。足利義満との関係、日野業子や斯波義将とのつながり、南朝勢力との確執、そして地元宗教勢力との調和。これらの要素が絡み合って、一つの大きな物語を形作っている。
すべてが事実とは言えないかもしれない。しかし、そこには確実に一つの真実がある。それは、一人の僧侶が「遼遠の境」に向かい、新たな宗教的拠点を築き上げたことである。
この瑞泉寺こそが、後の時代に井波を北陸浄土真宗の中心地へと押し上げ、さらには一向一揆の重要な拠点となり、そして現在に至るまで続く井波彫刻の礎となったのである。
綽如上人が杉谷の庵で見上げた夜空に、どんな思いを託したのだろうか。遙か遠い都への郷愁か、それとも新天地への希望か。答えは知る由もないが、彼の蒔いた種は確実に芽吹き、やがて大きな花を咲かせることになるのである。
(瑞泉寺ものがたり2へ続く)